神島

潮騒が聞こえるネイチャーアイランド

神島は、鳥羽港の北東約14キロメートル、愛知県伊良湖岬の西方約3.5キロメートルの伊勢湾口に位置し、総面積は0.76平方キロメートル、周囲3.9キロメートルで、4有人離島のうち最も遠い島で、三島由紀夫の小説「潮騒」の舞台となったことで有名となりました。また、外海と接しており、特に太平洋側からの強い波浪等の自然的災害を大きく受けやすく、島全体が山地になっているため、港から山頂にかけて階段状の家々が密集し、漁村特有の集落を形成しています。島の南端部は、市が天然記念物に指定している石灰石が風化してできたカルスト地形があり、山の斜面を覆う真っ白でごつごつした岩肌は、長い年月がつくりあげた芸術品とも言えます。さらに、弁天岬という半島があり、この辺一体は、本市でも数少ない自然公園法の第1種特別地域に指定されています。交通体系については、市営定期船で佐田浜港から1日4運航しています。
産業については、漁業と観光の調和のとれた地域振興を目指しており、ウオーキングしに来訪する方も多くなっています。
神島の概要 ABOUT THIS ISLAND
面積
0.76平方キロメートル
周囲
3.9キロメートル
世帯数
133世帯
人口
255人(男118人、女137人)(令和8年1月末)
宿泊施設
旅館・ホテル・民宿など 1軒(収容能力 25人)
観光客数
11,545人(令和6年1月~令和7年12月)
観光スポット
八代神社、神島灯台、監的哨跡、カルスト地形、古里の浜

観光 SIGHTSEEING
定期船にのると、遠くからでも美しい三角形の島が見えます。 定期船のりばから集落を通って、八代神社~神島灯台(恋人の聖地に認定)~監的哨~カルスト地形~小中学校~古里の浜~神島漁港と回る島一周ウォーキングコースが人気です。(ゆっくり歩いて約2時間) 八代神社から三島由紀夫さんがお世話になったという寺田さん宅の道筋へ抜けるお手軽コースもあります。 ウォーキングには、山海荘のたこかつばーがーや弁当をお供にし、景色のいい神島灯台等で食べていただくのもお勧めです。
島の体験ツアー実施主体
自然観察
サシバ、アサギマダラの渡り
毎年10月5日前後を中心に、伊良湖岬を飛び立ったサシバやアサギマダラをみることができます。
サシバ
小型の鷹で、暖かい地域で冬を越すために10月頃神島に飛来します。
アサギマダラ
インド・オーストラリアを中心に分布する蝶です。気流に乗って移動します。 (写真)

ウミウ
冬になると、断崖に数千羽のウ類がねぐらをつくります。
文化と歴史 CULTURE & HISTORY
島の祭り
ゲーター祭(元旦夜明け)
グミの枝を束ねて2メートル程の輪にしたアワを島中の男達が竹で刺し、持ち上げて落とします。 諸悪を払う祭りとも、豊饒を祈る祭りともいわれており、三重県の無形民俗文化財に指定されていますが 現在は休止しています(令和3年3月現在)(写真)

獅子舞(1月4日)
島内にある三ヶ所の塚で舞が行われます。女獅子、男獅子が舞ったあと、おかめ、ひょっとこ、えびすの順で踊り、最後に三人が一緒に踊ります。
六日祭(弓祭り)(1月6日)
元旦から続く一連の行事のひとつです。松明行事と弓祭りがあり、八幡祭りとも呼ばれています。山積みされたすす竹・しめ縄・門松などに火をかけ、火の向こう側においた的に矢を射ます。
歎仏会(旧暦 3月25日)
寛政12年に大勢の島の漁師が遭難したこの日を供養の日として漁を休み、冥福を祈っています。
ゴクアゲ(6月11日)
身内の海女全員が、神の磯であるコヘロガミでアワビをとり、弁天社に供えます。
ヤリマショ船(12月)
小舟をつくり、カヤの葉で身体をなで、厄をつけて海に流します。
島の文学
- 三島由紀夫 「潮騒」
- 柳田 国男 「伊勢の海」(のちに「遊海島記」と改題)
- 庄野 潤三 「早春の神島」
- 椎名 誠 「わしらはあやしい探検隊」 など
島の伝説
「鯛の島伝説」
昔むかし、神島の南に村があり、人が住んでいる島があったが、地震と津波によって水没したため、以来「絶えの島」といわれていた。その後、鯛がよく釣れることから「鯛の島」と呼ばれるようになったとの伝説がある。現在では海図に鯛島礁と記載されており、神島の南約7kmの付近とされている。
その他「オタツ女臈」「神島の七不思議」
島ゆかりの偉人
藤原豊吉 Fujiwara Toyokichi 1892~1981
民間としてはじめて潜水艇開発を成し遂げた藤原豊吉。深海という未知の世界に挑んだのは、彼の生まれ育った環境が導いたのかもしれません。周囲を壮大な海で囲まれた神島で生まれた豊吉は、海の男として育ち、何度も恐ろしい目に会いました。神島は三大難所の一つとされる伊良湖水道にあり、その潮流の速さと暗礁の多さに、船舶の遭難は絶えることがありませんでした。彼は、海難救助と港湾海底土木作業に従事しようと、藤原海事工業所を設立しました。荒々しく恐ろしい海の底は、恐怖の場所であると同時に未知の世界でもあり、このことは新天地開発への第一歩でもあったのです。民間としてはじめて母船搭載式球筒型潜水調査機を完成させ、深海作業の能率を向上させるとともに、非常に危険とされていた深海での作業を安全にしました。その後も海底トンネルや架橋建設で、この調査機は大きな活躍をすることになりました。そして、国内のみならず東南アジアやアフリカ、旧ソ連までにも進出していったのです。
島の食
四季を通じて新鮮な魚介類が味わえます。 タイ、スズキ、サワラ、イワシ、アジ、サバ、イセエビ、アワビ、サザエ、うに、タコ(ひだこ、たこ飯)、アラメ(さんまのあらめ巻き)など
食事処
山海荘 電話番号0599-38-2032
市認定のとばーがーのうち、たこかつバーガーが食べられます。(要予約)
宿泊施設
下記から観光情報サイトから検索ください。
その他
- 無線電話発祥の地(大正3年 鳥羽・答志・神島)
世界で初めて無線電話を実用化しました。
関連リンク
パンフレットなどの請求について
鳥羽市の離島や観光情報のパンフレットのダウンロード・請求は鳥羽市観光情報サイトへどうぞ。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画経営室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1101
ファックス:0599-25-3111
メールフォームによるお問い合わせ






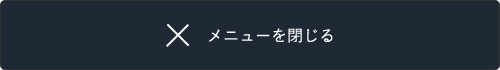




更新日:2026年02月17日