税額計算について(令和4年度)
1.税率表
|
区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
|
均等割* |
3,500円 |
2,500円 |
|
所得割(総合課税分) |
6% |
4% |
*みえ森と緑の県民税1,000円含む
2.税額控除(配当控除)
課税総所得金額が1,000万円以下の部分
|
種類 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
|
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
|
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託を除く) |
0.8% |
0.6% |
|
一般外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
課税総所得金額が1,000万円超の部分
|
種類 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
|
利益の配当等 |
0.8% |
0.6% |
|
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託を除く) |
0.4% |
0.3% |
|
一般外貨建等証券投資信託 |
0.2% |
0.15% |
3.税額控除(調整控除)
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のイ、ロのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
- イ.人的控除額の差の合計額
- ロ.合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用外となります。
調整控除の対象となる控除の種類と差額
|
控除の種類 |
差額 |
|---|---|
|
障害者控除(普通) |
1万円 |
|
障害者控除(特別) |
10万円 |
| 障害者控除(同居特別) | 22万円 |
| ひとり親控除(母) | 5万円 |
|
ひとり親控除(父) |
1万円* |
|
寡婦控除 |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
1万円 |
|
配偶者控除(一般) |
5万円 |
|
配偶者控除(老人) |
10万円 |
|
扶養控除(一般) |
5万円 |
|
扶養控除(特定) |
18万円 |
|
扶養控除(老人) |
10万円 |
|
扶養控除(同居老親) |
13万円 |
|
基礎控除 |
5万円* |
○配偶者控除
| 人的控除の種類 | 所得割の納税義務者の合計所得金額 | 差額 |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 900万円以下 | 5万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |
| 老人(70歳以上)控除対象配偶者 | 900万円以下 | 10万円 |
| 900万円超950万円以下 | 6万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 3万円 |
○配偶者特別控除
| 人的控除の種類 | 所得割の納税義務者の合計所得金額 | 差額 |
|---|---|---|
|
48万円超50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |
|
50万円超55万円未満 |
900万円以下 | 3万円* |
| 900万円超950万円以下 | 2万円* | |
| 950万円超1,000万円以下 | 1万円* |
*調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
4.配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
配当割額=特定配当等×5%(市3%、県2%)
株式等譲渡所得割額=特定株式等譲渡所得金額×5%(市3%、県2%)
※平成19年度より配当割・株式等譲渡所得割に係る還付金の充当規定が下記のとおり整備されました。
- (1)市民税所得割の額から控除しきれず還付すべき額(控除不足額)がある場合には、当該還付すべき額をその年度分の市民税均等割又は県民税所得割若しくは均等割に充当するものとする。
- (2)県民税所得割の額から控除しきれず還付すべき額(控除不足額)がある場合には、当該還付すべき額をその年度分の県民税均等割又は市民税所得割若しくは均等割に充当するものとする。
5.寄附金控除(いわゆる「ふるさと納税」など)
制度の概要
都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
※1複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による寄附金税額控除の適用について
確定申告を行う必要がない給与所得者などがふるさと納税を行う際、ワンストップ特例制度の申請をすると、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって住所地の市区町村へ通知を行うことで、確定申告などをすることなく寄附金控除の適用が受けられます。控除金額は所得税の控除相当額を含めて翌年度の市県民税から控除されます。
利用できるかた(次の条件をすべて満たしているかた)
- 確定申告などを行う必要のない給与所得などがあるかた
- 5団体以下の都道府県または市区町村に寄附を行ったかた
※特例の申請を行っていてもこれに該当されないかたや医療費控除などの申告をされるかたは、この特例は適用されませんので確定申告で寄附金控除の申告をしてください。
控除額の計算方法
|
区分 |
寄附金控除額 |
|
|---|---|---|
|
住民税 |
次の(1)と(2)の合計額を税額控除 (1)基本控除額〔寄附金-2,000円〕×10% (2)特例控除額〔寄附金-2,000円〕×〔90%-0~45%(所得税限界税率)〕 ※(2)の額については、個人住民税所得割の20%を限度 |
|
|
控除対象限度額 |
総所得金額等の30% |
|
|
所得税 |
〔寄附金-2,000円〕 |
|
|
控除対象限度額 |
総所得金額等の40% |
|
(例)給与収入700万円で夫婦・子ども2人(うち1人が特定扶養)の世帯で、3万円を寄附したときは
所得税額165,500円所得税の限界税率10%
1.所得税から・・・・・・2,800円
住民税額293,500円
2.住民税から・・・・・・25,200円
1.と2.合わせて28,000円が控除されます
平成23年分の寄附金から、所得税のみ2,000円を超える部分が寄附金控除の対象となります。
※控除額は、所得税と住民税の合計額です。
※所得税は寄附をした年分の所得税から、住民税は翌年度分の住民税から控除されます。
5.住民税を計算してみましょう
〔事例〕鳥羽太郎さん(46歳)の場合
給与の収入金額6,120,000円
家族
妻花子さん(43歳無収入)
長女桜子さん(19歳)
長男二郎さん(17歳)
社会保険料支払額581,400円
旧生命保険料支払額80,000円
|
給与所得 |
6,120,000×80%-440,000=4,456,000 |
(1) |
|---|---|---|
|
所得控除 |
社会保険料控除581,400 |
(2) |
|
生命保険料控除35,000 |
(3) |
|
|
配偶者控除330,000 |
(4) |
|
|
扶養控除450,000+330,000=780,000 |
(5) |
|
|
基礎控除430,000 |
(6) |
|
|
課税所得金額 |
(1)-[(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]=2,299,600 |
|
|
→2,299,000(1000円未満切捨) |
(7) |
|
|
市民税所得割額
|
(7)×市民税率=市民税所得割額 |
|
|
2,299,000×6%=137,940 |
(8) |
|
|
県民税所得割額
|
(7)×県民税率=県民税所得割額 |
|
|
2,299,000×4%=91,960 |
(9) |
|
|
調整控除 |
2,500 |
(10) |
|
市民税調整控除 |
1,500 |
(11) |
|
県民税調整控除 |
1,000 |
(12) |
|
市民税配当割控除額 |
|
(13) |
|
県民税配当割控除額 |
|
(14) |
|
市民税額 |
(8)-(11)-(13)+均等割額 |
|
|
137,940-1,500+3,500=139,900(百円未満切捨) |
(15) |
|
|
県民税額 |
(9)-(12)-(14)+均等割額 |
|
|
91,960-1,000+2,500=93,400(百円未満切捨) |
(16) |
|
|
市・県民税年税額 |
(15)+(16) |
|
|
139,900+93,400=233,300 |
|
※給与所得の計算は「所得金額について」をご覧ください。






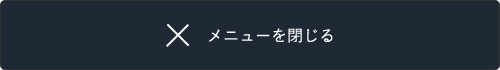




更新日:2022年04月14日