鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金
鳥羽市では、鳥羽市の地域課題の解決に向けた調査研究を行う学生団体や研究者等を対象に、調査研究に要する費用に対して補助金を交付します。
補助対象者
大学等に所属する学生団体または教授等。
なお、複数人または共同で調査研究を行う場合は、その団体の代表者を補助対象者とします。
補助対象事業
鳥羽市の地域課題の解決に向けた解決法策の提言または具体的な研究を行う事業で、鳥羽市長が認めるもの。
補助対象経費及び補助限度額等
補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は以下のとおりです。
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 |
|
報償費 宿泊費(鳥羽市内の宿泊施設を利用する場合のみ補助対象経費とする。) |
10分の10 | 10万円 |
※補助金の額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とします。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
※国、都道府県等から補助金等が交付されている場合は、対象経費から交付額を控除します。
補助対象期間
補助金の交付の決定を受けた日から該当年度の3月31日まで。
補助金交付要綱
鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 489.5KB)
調査研究テーマ 参考例
鳥羽市が解決を目指す地域課題を掲載しております。調査研究テーマの検討材料にご使用ください。
※この一覧はあくまで参考例です。こちらに記載されていない地域課題をテーマとして設定していただいても問題ございません。
「まちのカルテ」
地区ごとの地域課題のほか、生活情報やコミュニティなどの様々な情報をまとめた「まちのカルテ」を、下記のホームページよりご覧いただけます。掲載されている課題や情報は、地域の社会資源や地域住民の皆さまとの話し合いを通じて把握しており、適宜内容の見直し・更新を行っております。
研究調査の参考資料として、ぜひご活用ください。
申請方法
フォームから申請する場合
鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金 申請フォーム
調査研究開始の2週間前を目安に、下記フォームにて申請してください。
本申請にあたり、以下のものをご準備ください。なお、画像・ファイル添付が必要となります。
・調査研究構成員名簿(Excelファイル:9.1KB) ※任意様式です。
・代表者の顔写真付き身分証明書
・代表者の大学等に所属していることの証明書(学生証等)

申請フォームQRコード (クリックでフォームに入れます。)
鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金 変更申請フォーム
補助事業の内容・計画に変更が生じた場合は、速やかに下記フォームにて変更申請してください。
本申請にあたり、以下のものをご準備ください。なお、ファイル添付が必要な場合があります。
【番号等を確認するために必要なもの】
・補助金等交付決定通知書
【添付が必要なもの】
・行程表(当初から変更がある場合)
・調査研究構成員名簿(当初から変更がある場合)

変更申請フォームQRコード (クリックでフォームに入れます。)
鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金 実績報告フォーム
調査研究終了後、速やかに下記フォームにて実績報告を行ってください。
本申請にあたり、以下のものをご準備ください。なお、画像・ファイル添付が必要となります。
【番号等を確認するために必要なもの】
・補助金等交付決定通知書
・事業変更承認通知書(変更承認を受けた場合)
【添付が必要なもの】
・調査研究成果書 ※調査研究の詳細がわかる資料を任意様式でご提出ください。なお、成果書はHPに掲載いたします。
・補助事業に係る領収書
・補助金の振込先口座情報
※請求書は記入及び押印のうえ、下記事務局まで郵送してください。
・補助金等交付請求書(変更承認を受けていない方はこちら)(Wordファイル:44.7KB)
・補助金等交付請求書(変更承認を受けた方はこちら)(Wordファイル:46KB)
【郵送先】
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 鳥羽市役所観光商工課 観光係 宛

実績報告フォームQRコード (クリックでフォームに入れます。)
書類を作成して申請する場合
下記より申請様式をダウンロードし、必要書類をメールまたは郵送にて提出してください。
【メール送付先】
kanko@city.toba.lg.jp 鳥羽市役所観光商工課 観光係 宛
【郵送先】
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 鳥羽市役所観光商工課 観光係 宛
交付申請書類
調査研究開始の2週間前を目安に必要書類を提出してください。
・調査研究計画書(様式第1号) (Wordファイル: 15.5KB)
・収支予算書(様式第2号) (Excelファイル: 14.0KB)
・事業主体概要調書(様式第3号) (Wordファイル: 20.0KB)
・代表者の大学に所属していることの証明書(学生証等)の写し
・代表者の顔写真付き身分証明書の写し
※調査研究構成員名簿は任意様式です。
事業変更承認申請書類
補助事業について、内容・計画に変更が生じた場合は、速やかに必要書類を提出してください。
・変更事項を反映した書類等
実績報告書類
事業終了後、速やかに必要書類を提出してください。
・補助事業等実績報告書(変更承認を受けていない方はこちら) (Wordファイル: 14.5KB)
・補助事業等実績報告書(変更承認を受けた方はこちら) (Wordファイル: 14.5KB)
・調査研究報告書(様式第4号) (Wordファイル: 17.0KB)
・収支決算書(様式第5号) (Excelファイル: 13.0KB)
・調査研究成果書
・補助事業に係る領収書(コピー可)
・鳥羽市合宿補助事業アンケート (Wordファイル: 23.2KB)
・補助金等交付請求書(変更承認を受けていない方はこちら) (Wordファイル: 44.7KB)
・補助金等交付請求書(変更承認を受けた方はこちら) (Wordファイル: 46.0KB)
・振込先の通帳(口座情報がわかる部分)の写し
※調査研究成果書は、任意様式です。調査研究の詳細がわかる資料をご提出ください。なお、成果書はHPに掲載いたします。
過去の研究調査
令和7年度
| 団体名 | 調査研究名 | |
| 1 | 名古屋外国語大学 | 2025年度フランス語学科鳥羽研修 |
| 2 |
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 |
「こどもの居場所づくり」が地域のコンテクストに与える影響についてのフィールドワーク |
| 3 |
三重大学大学院 地域イノベーション学研究科 |
鳥羽市における家庭に困難を抱える子どもと地域支援のつながりに関する調査研究 |
| 4 |
大阪公立大学 PBL演習(環境学)調査チーム |
鳥羽市相差地区災害用井戸調査 |
| 5 |
京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 生活文化学研究室 |
文化的景観の観点から見た鳥羽市石鏡町の調査研究 |
| 6 | 一般社団法人まちあそびラボ | 鳥羽駅の再開発と実践アイデアコンペによる地域内外の連携について |
| 7 | 答志島和具お盆合宿実行委員会 | お盆合宿in答志島2025 |
| 8 | 島プロジェクトin鳥羽 | 島プロジェクトin鳥羽夏渡島 |
| 9 |
三重大学教育学部 家庭経営研究室 |
離島・僻地教育における地域住民の教育ニーズに関する研究:鳥羽市答志島での調査を通じて |
| 10 |
大阪大学 人文地理学教室有志 |
離島小学校における地域教育・観光教育の持続可能性調査 |
| 11 |
三重大学教職大学院 へき地複式教育研究ゼミ |
学校とともに歩む、これからの地域づくり |
| 12 | 食と観光実践:皇學館大学 | 食と観光実践:皇學館大学 |
| 13 | 食と観光実践:四日市大学 | 食と観光実践:四日市大学 |
| 14 | 22世紀奈佐の浜プロジェクト 学生部会 | 2025年度 答志島合宿 |
| 15 | 東大生地方創生コンソーシアム | 鳥羽市内の小中学生を対象としたワークショップ企画・提案および発表に関するフィールドワーク調査 |
| 16 | 女子美術大学 | 鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト「海女と芸術文化」 |
| 17 | 防災教材と学びの旅プロジェクト | 海のまち鳥羽~防災と学びの旅~ |
| 18 |
牡蠣殻ワークショップ 千葉大学チーム |
鳥羽市における牡蠣殻アップサイクルを通じた資源循環型まちづくりに関する調査研究 |
調査研究詳細
| 調査研究名:2025年度フランス語学科鳥羽研修
実施内容 当事業補助金申請書に記載した事業内容の通り、本学フランス語学科2年次生を対象として、令和7年6月7日から6月8日の一泊二日で、「鳥羽研修」を実施、完了することができた。事前指導ならびに事前の取組みとして、グループごとに「鳥羽市における観光業」、「海女文化」、「離島(と観光)」、「漁業(と継承)」、「海洋漂着物」、「体験プロジェクト(と移住・人口減少対策)」、のテーマに基づき、鳥羽市の例を含め、これらの業界における現状、課題、展望について調べ、グループで話し合いを重ねて考察し、プレゼンテーションに向けたパワーポイント資料の作成に取り組んだ。二日間の研修中、初日には鳥羽市観光商工課にご所属のカゾ氏による鳥羽市の観光業にまつわる講演と、鳥羽市立「海の博物館」を見学するだけでなく、実際にお二人の海女の方-女性海女のみの地区で活躍されている方-から、直接体験談を伺う機会に恵まれた。初日の夜には宿泊先にて各グループによるプレゼン発表を行い、全員が各業界における課題や展望について情報を共有することができた。 一方で、二日目には答志島にて海洋漂着物の収集活動を予定していたものの朝から雨天となり、開始予定1時間前まで雨雲レーダー等を確認しつつ実施可能性を模索したものの、雨足が強まり、やむをえず中止の判断に至った。 調査結果 今年度は一部予定変更が生じたものの、概ね、鳥羽市における地域密着型のフィールドワークを実践することができた。事後のアンケートより把握できたこととしては、事前に調べ学習等から理解していた事象や情報について、鳥羽市を例に、自らの目で直に見て、耳で聞いて経験することで、多くの学生が多様な課題を自分事として捉えることができるようになったこと、新たな視点を多く得られたこと、そして鳥羽市の魅力を知り得たこと等が、意見として多く挙がった。普段の生活圏・生活リズムではなかなか取り入れ難い、離島で時間を過ごすという、大変貴重な経験が得られたことは、現代の若者にとって非常に良い機会になったことが窺える。 また、このフィールドワークを通して完成させた、各グループの取組み発表の結果からは、鳥羽市に限らず、いずれの課題にも人口減少の問題が背景に確認できること、若者の海離れ等が指摘されると同時に、観光業の観点においては、とりわけ、同じ東海地方であるにもかかわらず、岐阜県からの観光客が非常に少ないことが明らかになった。 課題解決の提言 課題として指摘されたものの内、例えば、人口減少については、他の市区町村の対策を例に、鳥羽市から都心部へ就職する人や鳥羽市へ移住してきた人を対象に、一定の条件を付して通勤のための交通費支援を行うことが一つの方法として出された。他にも若者の海離れについては、「タイパ」が悪いといった負のイメージを払拭するため、海の新たなイメージを創出することや、比較的海に関心の高い高校生に向けて情報発信することや、小学生を持つ家庭向けの、鳥羽市の食とアクティビティ、歴史文化遺産と結びつけたツアーを積極的に制作することなどが、一つの提案として挙がった。 また、同じ東海地方であるにもかかわらず、岐阜県からの観光客が非常に少ない点については、鉄道網の「乗り換え」「接続」といった課題解決に向け、例えば、岐阜県の主要な駅から直通のバスを試験的に運行し、交通の便を良くする工夫を凝らすことが試みとして挙がった。 |
| 調査研究名:「こどもの居場所づくり」が地域のコンテクストに与える影響についてのフィールドワーク
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:鳥羽市における家庭に困難を抱える子どもと地域支援のつながりに関する調査研究
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:鳥羽市相差地区災害用井戸調査
実施内容 鳥羽市相差地区にて井戸利用の聞き取り調査および井戸分布の現地調査を行い、それを地図化することで、地域防災の向上を試みた。 調査結果 ・相差地区の北部から南部にかけて井戸が分布している反面、東西の地区(相差漁港、畔蛸地区)の井戸分布が手薄である。 ・災害時協力井戸のプレートがあるものの、サイズが小さく気づきにくい 課題解決の提言 ・分布が手薄な地域については、自治会の支援を受けつつ、井戸の洗い出し作業を行う必要がある。 ・プレートのサイズを大きくする(参考までに神奈川県秦野市のプレートは1mサイズです)。 |
| 調査研究名:文化的景観の観点から見た鳥羽市石鏡町の調査研究
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:鳥羽駅の再開発と実践アイデアコンペによる地域内外の連携について
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:お盆合宿in答志島2025
実施内容 全国から募集した大学生を島へ招待し、整備された空き家で集団生活をしながら、答志島和具の様々なお盆行事の準備のお手伝い・参加を行います。また、その隙間時間で島の人々と関わったり、島の散策を行ったりすることで、始めて島に来る大学生が答志島の魅力を知る機会を設けます。 調査結果 本調査研究における活動を通じて、活動以前から認識されていた課題に加え、新たに具体的に明らかとなった課題を以下に示す。
課題解決の提言 本調査研究を通じて明らかとなった課題、すなわち1.答志島和具における伝統行事の担い手不足および当事者のモチベーション低下による行事縮小の危機、2.大学生年代の不足による地域活力や子供たちの成長機会の制約、は地域の持続可能性に直結する重要な課題である。これらを解決するためには、短期的な施策よりも、継続性を重視した仕組みづくりが不可欠である。
|
| 調査研究名:島プロジェクトin鳥羽夏渡島
実施内容 鳥羽市離島地域の地域課題に対して、大学生が現地での実践的な取り組みを行うことにより、地域課題を把握し、課題解決の一端を担うとともに、地域住民への貢献のあり方や意義を探究する。
調査結果 A)空き家の維持に関する課題
課題解決の提言 ア)学生の滞在について
|
| 調査研究名:離島・僻地教育における地域住民の教育ニーズに関する研究:鳥羽市答志島での調査を通じて
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:離島小学校における地域教育・観光教育の持続可能性調査
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:学校とともに歩む、これからの地域づくり
実施内容 ◎ 「へき地複式教育と地域づくりを考える交流フォーラム」 ~学校と共に歩む これからの地域づくり~を実施 令和7年10月31日 ~ 令和7 年11月1日 ○ 鳥羽市立菅島小学校での授業参観、特色ある教育活動の説明と意見交流会「島っ子ガイドフェスティバル」に参加 ○ 交流会 参加者:桑名市、伊賀市の学校関係者や地域住民 場 所:菅島コミュニティーアリーナ和室 内 容: 三重大学教育学部教職大学院生が担当 ・ 自己紹介 ・ 団体や個人の取り組みの紹介 ・ 地域課題の設定と解決方向のワークショップ ○ 調査研究 ・ ワークショップでの記録の分析 ・ アンケート調査やインタビューの記録の分析 調査結果 1 「菅島交流フォーラム」交流会(話し合い)から見えた 課題 (1)教育の現場・複式授業について • 複式授業のタイムマネジメントの難しさ • 新任教員への負担が大きく、研修や支援体制が不足 • 少人数職員での対応の限界 • 授業スタイルやルールづくりが不可欠だが、継続的な工夫が必要
(2)地域文化・学校との関わり • 学校が地域に協力を「お願いするだけ」では進展しない • 地域や保護者の主体的関わりが不可欠だが、担い手の確保が課題 • 行事や活動の継続に負担がかかり、働き方改革とのバランスが難しい • 新しい取り組みが時間とともに課題化する循環
(3)地域づくり・小規模校の未来 • 小学校の存在が地域のまとまりに直結しているが、存続の不安がある • 地域間で課題は共通しているが、対応力に差がある • 若い世代の関わりが減少し、地域活動の担い手不足が顕著 • 学校と地域の立場が一致しないと運営が困難になる 課題解決の提言 (1)教育の現場・複式授業について • 複式教育の専門的研修の充実 新任教員向けに、複式授業のタイムマネジメントや工夫を学べる研修を体系化する。 • 支援ネットワークの構築 経験者が新任を支える「伴走型支援」を地域や教育委員会と連携して整備する。 • 授業ルールの共有化 学校内で授業スタイルやルールを明文化し、教師間で共有することで安定した授業運営を可能にする。
(2)地域文化・学校との関わり • 地域主体の協働文化の強化 学校が「お願いする」だけでなく、地域が主体的に企画・運営に関わる仕組みをつくる。 • 行事の持続可能化 行事の規模や方法を見直し、負担を軽減しながら特色を維持する。 • 世代間交流の促進 若い世代が関わりやすい形(短時間参加、役割分担の工夫)を導入し、担い手不足を補う。
(3)地域づくり・小規模校の未来 • 学校存続のための地域戦略 小学校が地域の核であることを明確にし、行政や地域で存続の方策を模索する。 • 地域間連携の強化 同様の課題を抱える地域同士で情報交換や共同企画を行い、知恵を共有する。 • 若い世代の巻き込み 地域教育活動に若者が参加できる仕組み(ボランティア、交流イベント)を設ける。 • 学校と地域の立場調整 学校運営協議会などを活用し、立場の違いをすり合わせる場を定期的に設ける。
3 総合的な方向性 • 複式教育の課題は「専門性の確立」と「支援体制の整備」が鍵。 • 地域文化との関わりは「主体性」「持続可能性」「世代間交流」がポイント。 • 小規模校の未来は「学校存続」「地域間連携」「若者の参画」「立場調整」が重要。 |
| 調査研究名:食と観光実践:皇學館大学
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:食と観光実践:四日市大学
実施内容 本調査研究では、答志島における観光および⾷に着目し、誘客につなげるための手法を検討した。 調査では、鳥羽市役所、市水産研究所、海の博物館などの担当者様から、離島の歴史や水産資源に関するレクチャーおよび聞き取りを行った。またフィールドワークとして、答志島に渡り「島の旅社」様に島内をご案内頂きながら、地域資源の把握および課題の抽出を進めた。ここまでのレクチャーやフィールドワークの内容を踏まえ、学生にはポスター作りを事例に、現在の課題、誘客に向けたターゲット層、何を伝えたいのか、どのように誘客につなげるのかについて、グループワークとして検討してもらった。完成したポスターは、鳥羽マリンターミナル内で発表会および優秀賞の選定を実施した。 調査結果 この調査研究では、誘客につなげるための手法の検討を行う中で、現在見られる課題点に関しても整理した。学生からは、答志島の魅力に関して、三重県内居住者および三重県内を訪れた観光客に十分に伝わっていないことが指摘された。また、答志島の自然・アクティビティ・食材・人と人とのつながりがアピールポイントであり、三重県内居住者はもちろんのこと、観光や仕事で三重県を訪れた人、三重県外の居住者なども含めて、多くの人にわかりやすく伝えていく必要性についても報告された。 課題解決の提言 この調査研究を通して、答志島への誘客につなげるためには、答志島の魅力を多くの方に知ってもらうなど、訪れてもらうためのきっかけづくりが必要であると学生から報告があった。 これらの報告を踏まえ、答志島の魅力に関するPRポスターをチームごとに作成し、完成したポスターは鳥羽マリンターミナル内で発表会および優秀賞の選定を行った。優秀賞チームのポスターは、鳥羽マリンターミナルに掲示していただくことになっており、三重県内の学生たちが取り組む地域活動発表会「みえまちキャンパス」においても発表を予定するなど、今後も答志島の魅⼒の発信を続けるつもりである。 |
| 調査研究名:2025年度 答志島合宿
実施内容 ・奈佐の浜清掃活動に参加し、漂着ゴミ問題の現状を確かめた。 ・答志島島民や漁業者などと話し合い、桃取町元気プロジェクトによるアマモ場再生活動のありかたについて考えた。 ・学生交流会を実施し、ゴミ問題に留まらない流域のつながりと、課題に対する対策について考えた。 調査結果 ・伊勢湾には年間12,000トンのごみが流入し、そのうち約4分の1が答志島桃取の奈佐の浜に流れつく。 ・答志島のノリ養殖においてごみが海苔網に絡まり損壊するなどの被害が出ており、鳥羽市の産業にも影響を及ぼしうる。 ・漂着ごみは都市や山間部を含む流域全体を発生源とし、廃棄物管理や人工林の放置といった問題とも関連している。 ・したがって、漂着ゴミ問題の解決には愛知・岐阜・三重を中心とした地域間連携が必須である。 ・また、答志島桃取では、海の生物多様性を守るためにアマモ場再生活動が実施されてきたが、担い手不足の問題に直面している。 課題解決の提言 ・鳥羽市の漂着ゴミ問題を含む各地域の課題が互いに関連し合うことを周知し、各地域と連携して継続的な情報提供や対策実施に取り組む。 ・例として、観光案内と併せた地域課題の提起による情報発信のほか、漂着ゴミや生態系をモニタリングし上流地域における森林や廃棄物管理などの施策に反映させることなどが挙げられる。 ・また、伊勢湾の生物多様性保護のため、答志島桃取におけるアマモ場再生活動等において島民、漁業者、市外有志などと協力して活動を継続・活発化していく。 |
| 調査研究名:鳥羽市内の小中学生を対象としたワークショップ企画・提案および発表に関するフィールドワーク調査
実施内容 フィールドワークの実施に先立ち、参加メンバーはインターネットや専門文献を通じた事前調査を行い、鳥羽の地域的な特色を深く分析した。この調査結果を踏まえ、鳥羽市内の子どもたちを対象とした独自のワークショップ企画案を立案した。フィールドワーク当日は、現地で地域の子ども向けイベントが開催されていたため、その会場の一画をお借りし企画提案を発表する機会を得ることができた。イベントにご来場いただいた小学生からご高齢の方まで、幅広い世代の方々に発表をご清聴いただき、各提案に対するご意見・ご感想をアンケート形式で収集することができた。本活動を通じて、企画案に対する多角的な視点からの貴重なフィードバックを得ることができた。 調査結果 本フィールドワークおよび企画発表後のアンケート結果に基づき、ワークショップの実現に向けた以下の2点が主要な課題として明確になった。 課題解決の提言 今回、私たちからは以下の2つのワークショップ企画を提案した。 |
| 調査研究名:鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト「海女と芸術文化」
実施内容
調査結果
課題解決の提言
|
| 調査研究名:海のまち鳥羽~防災と学びの旅~
実施内容 地域と連携した実践的な防災教育の一環として、事前学習および現地フィールドワークを中心とする調査を実施した。事前学習では、鳥羽市のハザードマップ、地域防災計画、「myマップラン」等の関連資料を調査し、自治体間の取り組み比較を行いながら、地域特性に基づく防災上の課題を整理した。その課題をもとに、住民の状況や行動選択を踏まえたゲーム形式の防災教材の製作に向けた準備を進めた。 調査結果 1.地形に基づく避難上の構造的課題 ・住宅地と避難所の地理的条件で、混雑・通行障害が発生しても、他の避難ルートを選択することが難しい地域がある。 ・夜間の見通しの悪い道、足元の危険箇所が存在する。 ・海上・島部の船舶利用者に対する具体的な避難誘導ルールがない。 ・夜間・降雨時・高潮期など、時間帯や天候、季節の複合的要因によって避難へのリスクが高まる
以上の調査結果に加えて防災を「怖い・難しい」と捉えてしまう心理的ハードルが存在することが明らかになった。これらの課題に対しては、行政・市民・観光事業者が一体となって防災行動を理解・共有し、地域全体での実効性ある行動につなげる防災教育の仕組みが求められる。 課題解決の提言 以上4点の課題に応える手法として、すごろく形式の防災教材の開発・活用を提案する。本教材は、以下の三点で鳥羽市の防災課題解決に貢献する。 |
| 調査研究名:鳥羽市における牡蠣殻アップサイクルを通じた資源循環型まちづくりに関する調査研究
実施内容 11月26~27日 プレゼンボード作成 11月28日 イベント当日 牡蠣殻ワークショップ 12月 報告書作成 調査結果 今回実施した市民参加型ワークショップを通じて、いくつかの課題がより明確になった。第一に、鳥羽市民が、鳥羽市内でどれほどの量のかき殻が「鳥羽かき殻加工センター」においてアップサイクルされているのかを、十分に認識していない実態が明らかになった。 また、ワークショップでは親子を中心に、アクティビティとして「かき殻飛ばし」を体験してもらい、その後に当該かき殻がアップサイクルに活用されていることを説明し、あわせてケアシェル株式会社が製造したかき殻由来の肥料を配布した。しかし、「かき殻飛ばし」の体験自体は楽しんでもらえた一方で、その後に行ったかき殻の利活用に関する説明には、あまり耳を傾けてもらえない場面が見られた。この点は、かき殻のアップサイクルに対する理解を深めるうえでの課題であると考えられる。 課題解決の提言 上記の課題を解決するためには、「鳥羽かき殻加工センター」および「ケアシェル株式会社」の知名度向上を目的とした広報活動が必要である。また、「ケアシェル株式会社」については、日仏海洋学シンポジウム講演会で講演を行った実績などを紹介する内容を盛り込んだパンフレットを作成することが考えられる。 これらのパンフレットを、地元の学校や駅などで住民に向けて配布するとともに、観光地において観光客に配布することで、鳥羽市内における認知度の向上だけでなく、他地域の人々にもその取り組みを知ってもらうことが可能になると考えられる。 |
令和6年度
| 団体名 | 調査研究名 | |
| 1 |
名古屋外国語大学 フランス語学科 |
2024年度フランス語学科鳥羽研修 |
| 2 |
三重大学大学院 教職志望学生×インプロプロジェクトin三重 |
インプロ(即興演劇)を活用した小学生と教職志望学生の交流を通じた「表現」コミュニティの創出に関する実践的研究 |
| 3 |
三重大学 地域イノベーション学研究科 |
鳥羽市で見つかる海の生き物や,「鳥羽市海のレッドデータブック2023」を活用した海洋教育の提案と,海洋教育を通じた子どもたちの定住意欲に関する研究 |
| 4 |
三重大学 教育学部 |
鳥羽市の魅力を踏まえたビジネスモデルの構築 |
| 5 |
皇學館大学 伊勢志摩共生学実習A |
伊勢志摩共生学実習A 離島における関係人口創出ための情報発信実習 |
| 6 |
國學院大學 観光まちづくり学部(下村ゼミ) |
国立公園におけるエコツアープログラムのあり方 |
| 7 |
島プロジェクトin鳥羽 |
島プロジェクトin鳥羽夏渡島 |
| 8 |
京都府立大学大学院 生命環境科学研究科生活文化学研究室 |
鳥羽市内の漁村における漁撈小屋の調査研究 |
| 9 |
22世紀奈佐の浜プロジェクト学生部会 |
2024年度 答志島合宿 |
| 10 | 女子美術大学 | 鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト |
| 11 |
茨城大学 人文社会科学部野田真里教授研究室 |
鳥羽市・答志島SDGsフィールドワーク2024 |
| 12 |
東大生地方創生コンソーシアム |
鳥羽なかまち地域課題研究合宿 |
| 13 | 一般社団法人まちあそびラボ | 鳥羽駅前再開発にあたる事前調査 |
調査研究詳細
| 調査研究名:2024年度フランス語学科鳥羽研修
実施内容 本学フランス語学科2年次生を対象として、令和6年5月31日から6月1日の一泊二日で、「鳥羽研修」を実施、完了することができた。事前指導ならびに事前の取組みとして、グループごとに「観光業」、「フランス人・外国人を対象とした観光業」、「海女文化」、「離島(と観光)」、「漁業(と継承)」、「海洋漂着物」のテーマに基づき、鳥羽市の例を含め、これらの業界における現状、課題、展望について調べ、グループで話し合いを重ねて考察し、プレゼンテーションに向けたパワーポイント資料の作成に取り組んだ。二日間の研修中、初日には鳥羽市観光商工課にご所属のカゾ氏による鳥羽市の観光業にまつわる講演と、鳥羽市立「海の博物館」を見学するだけでなく、実際にお二人の海女の方から-ベテランの方と移住した若い方-、直接体験談を伺う機会に恵まれた。二日目には答志島にて海洋漂着物の収集活動を体験し、関係の皆様からお力添えいただいたおかげで、予定通り、鳥羽市における地域密着型のフィールドワークを実践することができた。事後のアンケートより把握できたこととしては、事前に知識として理解していた事象を自ら経験することで、多くの学生が多様な課題を自分事として捉えることができるようになったこと、現地において直に目で見て、耳で聞いて新たな視点を多く得られたこと、そして普段の生活圏・生活リズムではなかなか取り入れ難い、離島で時間を過ごすという、大変貴重な経験が得られたこと、等が挙げられる。 また、このフィールドワークを通して完成させた、各グループの取組み発表の結果、それぞれのテーマについて、学生達なりの展望を示すに至り、発表内容については学生間での評価活動も行った。展望の具体的な内容としては、観光業については、例えば日本人とフランス人の観光に対する価値観の違いに着目し、「今、この場所だから経験できる」魅力をよりアピールし、インスタグラムなどで「日本の〇〇」のようなハッシュタグを作り、多言語で情報発信を行うこと、漁業については、何よりも漁業に興味を持つことが必要だという指摘や漁業に触れ合う場をもっと設ける提案、海洋漂着物に関しては、「海ごみゼロウィークin愛知」のような活動をもっと広げ、誰もが身近な場所で、目に見える成果として参加できるようなボランティア活動を活発に行うことや、離島の活性化については、現行の離島留学の中に、夏休みという短期間でのファミリー離島留学(親はヴァカンスとして)を取り入れる提案、等々がなされた。 調査結果 観光業では、フランス人に着目する場合、日本特有の場所や物に関心を抱き、文化的な体験を求めている傾向があるため、視覚効果を重視した多言語での情報発信がもっと必要になり、鳥羽観光として有名な鳥羽水族館の目玉の一つである二頭のラッコに注目すると、メイが今年20歳という平均寿命に到達するため、将来的な懸念が増しつつあり、そもそもラッコは繁殖の難しさや海洋汚染、地球温暖化の影響を受けて個体数が減少していること、離島の一つである答志島では過去12年で21%の人口減少が進み、その内若者の減少率が5割を占めているために伝統産業の継承問題や医療機関の減少問題が見受けられること、海女文化を含む漁業においては、人口減少と同時に生産者の高齢化、海域の温暖化、生産コストの増大といった課題に直面していること、海洋漂着物の点ではそもそも日本のリサイクル率が世界的に低く、鳥羽市においては生活系の漂着ごみが漁業系に次いで多い、という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 観光業については、例えば日本人とフランス人の観光に対する価値観の違いに配慮し、「今、この場所だから経験できる」という魅力をこれまで以上にアピールし、インスタグラムなどで「日本の〇〇」のようなハッシュタグを作り、多言語で情報発信を行うこと、漁業については、何よりも多くの人が漁業に興味を持つことが必要であるため、漁業に触れ合う場をもっと設けてイベント情報を発信することや、海洋漂着物に関しては、「海ごみゼロウィークin愛知」のような活動をさらに広げ、誰もが身近な場所で、目に見える成果として参加できるようなボランティア活動を活発に行うこと、離島の活性化については、現行の離島留学の中に、夏休みという短期間でのファミリー離島留学(親はヴァカンスとして)を取り入れること、等々。 |
| 調査研究名:インプロ(即興演劇)を活用した小学生と教職志望学生の交流を通じた「表現」コミュニティの創出に関する実践的研究
実施内容 1. 7〜10月:ワークショップのデザイン 〇プロジェクトチームの大学生メンバーとのミーティング ・本実践研究の目的および実践方向性の共有 ・"異年齢"交流を重視するため、学年問わず小学生を広く募集 ・学校内外の小学生対象の行事等との重なりも考慮し日程・会場を決定 〇チラシの作成、参加小学生の募集 ・鳥羽市教育委員会後援申請 ・9月、参加小学生の募集を開始 ・鳥羽市教育委員会様を介して市内の小学生全員にチラシを配布、「広報とば」への情報掲載 ・鳥羽市民体育館、市役所、図書館、スーパーマーケット等でのチラシ掲示・配布を依頼 ・参加申込小学生及びその保護者宛に、当日の案内、調査概要・ 同意書の様式を送付
2. ワークショップの実施・省察1(11〜翌年1月) 〇11月16日(土曜日)、鳥羽市民体育館にて、ワークショップ実践を実施 ・6名の子どもたちが参加 〇ワークショップ終了後、参加大学生7名とのグループ省察1の実施 ・子どもたちの「表現」を引き出すための自身の働きかけ、そして自身の関わりが子どもたち同士のつながりにいかに結びついていたのかを言語化し、共有 ・保護者へのアンケート調査回答依頼 3. 省察2、分析、まとめ(2〜3月) 〇2月9日(日曜日)参加大学生7名とのグループ省察2の実施 ・他のワークショップ実践とも比較しながら本ワークショップを振り返る 〇以上をデータとして用いて、子どもたちと大学生との関わりの過程、関わりを通した学びのありようを分析し、報告書を作成 調査結果 調査研究により、 1. 子どもたちの「表現」の難しさ ・初対面の人と関わること(対・子ども、対・大学生) ・"自分のことば"で表現すること 2. 子どもたちの会場までの移動の難しさ が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 1. 子ども参加型・異年齢交流型の文化芸術活動の継続 学校・学級とは異なる集団のなかで、初対面の人との関係を築きあげていく機会が必要と考えます。その際、この相手・この場では"自分のことば"をそのまま伝えても大丈夫だと思える安心感、そしてそうした安心な場でこそ醸成される子どもたちの自己肯定感を育んでいく必要があると考えます。また、そうした場を創出するた めに、本学の教職志望学生がいかにかかわり、教師としての力量を高めていけるかを今後も検討していきたいと考えております。 2. 市内各地での活動の展開、「表現」コミュニティの創出 今回ワークショップに参加してくれたのは、鳥羽小学校・ 安楽島小学校の子どもたちのみでした。子どもたちが会場まで来ること自体に大きなハードルがあることを痛感いたしました。今後、各小学校の近くの公共施設等をお借りして、市内全域でインプロワークショップを展開できればと考えております。 |
| 調査研究名:鳥羽市で見つかる海の生き物や,「鳥羽市海のレッドデータブック2023」を活用した海洋教育の提案と,海洋教育を通じた子どもたちの定住意欲に関する研究
実施内容 鳥羽市内の小中学校10校における海洋教育の実際の実施状況を調査し、実際に行われている海洋教育に関する子どもたちの学習効果・学習意欲等を調査した(3年生以上)。さらに海洋教育が子どもたちに与えている影響についても調査を行い、地域愛着や定住意欲を測った。 調査結果 各学校で海洋教育の実施は様々であり、地域との連携もまた様々であった。「鳥羽市海のレッドデータブック2023」の活用については、図書館においてあるだけの学校が多く、十分な活用がなされているとは言い難かった。また、本研究に関するアンケート調査で、子どもたちの意識にも教育活動が影響していることが明らかになった。 鳥羽市の小中学校に通う子どもたちの海洋に関する学習への意欲は高く、学習効果も高いことが明らかになった一方で、地域への愛着と定住意欲に関しては結果にばらつきがみられた。 アンケート結果から、地域資源を利活用した体験活動(教育活動)が地域愛着や定住意欲に影響を与える可能性があることが明らかとなり、その体験活動を地域の方々と連携して行うことでより効果的であることが明らかになった。 ふるさと教育としても活用できる海洋教育において、子どもたちの地域愛着や定住意欲に効果的な教育活動が体系的に行われているとは言い難く、結果として各学校によって地域愛着や定住意欲に差が出ているという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になった。 課題解決の提言 地域愛着や定住意欲に効果的な教育活動の実現には、地域との協力体制の構築や、教育プログラムの具体的なモデル化が必要となる。海洋教育が定住意欲に直接的な効果があるとは言い切れないが、海洋教育によって地域愛着を高めることで、後の定住に繋がる可能性がある。 各学校の海洋教育の実施の足並みをそろえることは難しいが、学習を交流する場を設けることで、「自分の知らなかった鳥羽」に触れることができ、地域の魅力の再発見につながるのではないかと考える。 今後の海洋教育においては、行政・教育機関・市民を繋ぐカウンターパートを設置し、地域で取り組む海洋教育の進める必要があると考える。 |
| 調査研究名:鳥羽市の魅力を踏まえたビジネスモデルの構築
実施内容 学生6名、教員3名で鳥羽市のいくつかの施設を訪問し、現状を調査し、その結果を踏まえて、学生目線で鳥羽市を活性化するヒントとなる2種の案を作成した。 調査結果 調査研究により、 ・伊勢志摩と括られることが多く鳥羽の印象が薄い ・若者をターゲットとしたSNSの発信が弱い という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 ・「伊勢志摩」には鳥羽市や南伊勢町等も含まれるとのことでしたが、一般の人にはそうは認識されていないので、鳥羽市の存在をアピールする工夫 ・鳥羽市として鳥羽市に国内外の訪問者を呼び込む取り組みをされていることを知りましたが、実際に若者層にはそうした取り組みの情報が届いていないということで、若者の意見を取り入れたSNS等での効果的な発信を行うこと |
| 調査研究名:伊勢志摩共生学実習A 離島における関係人口創出ための情報発信実習
実施内容 離島地域「答志島」の取材を行い、旅行サイトなどでは紹介されない魅力を探しや地域の方が紹介したい自慢の聞き取りを行い、離島を紹介するwebサイトの記事掲載を行いました。少子高齢化が進み伝統行事やイベントの参加者が少なくなることで継続が難しくなっています。また漁業や観光業の人出が不足していることを解消するため、取材した記事を発信することで、ただの観光だけではなく、全国の離島ファンや観光客へのプロモーションにつなげたほか、地域の魅力を伝えることで、地域のイベントや祭りなどにかかわる方や漁業体験する方、リピーターの方など観光客より深い関係人口と呼ばれる方の増加を図りました。また、答志島の魅力を関係人口が体験することで、ゆくゆくの移住促進となるよう協力したい。 りとふる掲載ページ:https://ritoful.com/archives/42443 調査結果 調査研究により、地域の方が見せたい魅力と、訪れた人が感じる魅力にギャップがあり、答志島の魅力が伝えきれていない。地域としては、人口減少・高齢化ですべてにおいて人手不足である、という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 答志島の魅力を発信するため、観光サイトなどでは紹介されない、地域の魅力(人のあたたかさや明るい子供たち。地域交流の拠点。歴史や文化。食事等)を離島の情報発信をするwebサイトで公開することで、離島好きの観光地候補としてプロモーションを行う。それにより実際に答志島を訪れる人が答志島ファン(関係人口)となる取り組みを継続していく必要がある。 |
| 調査研究名:国立公園におけるエコツアープログラムのあり方
実施内容 別添「全域が伊勢志摩国立公園に指定されている鳥羽市におけるエコツーリズムのあり方」のとおり。 調査結果 調査研究により、山地・森林域を含め、鳥羽市の自然環境の全体像を発信・活用するという点、また、資源活用・情報発信に際して、点的資源としての認識が中心であり、海・山・歴史などを複合して面的にストーリー(物語)化した活用・発信が十分ではないという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 沿岸・海域と山地・森林域の結びつけることへの取り組み、そして、それを空間展開するための計画・整備が必要である(詳細は別添) |
| 調査研究名:島プロジェクトin鳥羽夏渡島
実施内容 1.お盆合宿企画
調査結果 1.お盆合宿企画
6.島の加工品調査
課題解決の提言 1.お盆合宿企画
創作物という自己表現の間に、一つ自分が生まれ育った場所に関係するものを挟むことによる意味合いには、その地域への理解を深めていくこと、所属意識や愛着の醸成などがあり更にそれを外部の人と一緒に取り組むことでより一層認識することができる効果があると考える。特に子供達にとって効果的である。
|
| 調査研究名:鳥羽市内の漁村における漁撈小屋の調査研究
実施内容 石鏡の漁撈小屋「アミバサ」を中心に、神島・菅島の網作業小屋を含めて実測・聞き取り調査を行い、これらの形成過程を解明した。 調査結果 当調査研究により、漁撈小屋の詳細な形態や、その歴史的背景を明らかにした。またこの成果を通じて、鳥羽市各地の漁撈小屋は、集落の歴史や生活文化を反映する構築物であることを明らかにした。 このような漁撈小屋の景観的・文化的価値に対し、漁師の減少に伴う漁撈小屋の廃絶が起こり始めており、集落を特徴づける景観的・文化的資産の減少が課題となっている。 海女小屋が文化的資産として位置づけられている一方で、漁撈小屋の評価は遅れている。 課題解決の提言 漁撈小屋の景観的・文化的価値を定めること、またこれを同市における漁業や住民の魅力と結びつけて発信すること、など。 |
| 調査研究名:2024年度 答志島合宿
実施内容 ・NPO法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター講演の聴講 ・答志島の島民と交流し、文化や生業について学ぶ ・答志島 奈佐の浜にて海岸清掃とワークショップを実施 調査結果 島民からの聞き取りにより、ゴミで漁業に支障が生じ、鳥羽市の産業に損失が生じていることが分かりました。また、参加者聞き取りにより、三重県内外問わず、答志島のことは知っていてもゴミ問題は知らない者がほとんどであることが明らかになりました。 これまでの海岸清掃により、奈佐の浜の漂着ゴミが県内外の生活ごみ、不法投棄のゴミ、漁具、自然ゴミ等で構成されていることが分かっています。一時的な清掃活動ではなく、発生源である伊勢湾流域の市民が漂着ゴミを発生させないようにすることでしか問題が解決されないことが示唆されます。 課題解決の提言 まず、漂着ゴミ問題について周知するため、市として市民に広報するとともに、他県との協力体制を構築していく必要があると考えます。 また、観光客にゴミ問題への理解を深める機会を提供するため、清掃活動を観光の一環としたエコツーリズムの取り組みを提案します。例えば、「ゴミ拾いツアー」といったアクティビティを設定し、清掃活動を観光体験の一部とすることで、参加者の環境保護への意識を高めることが期待されます。 |
| 調査研究名:鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト
実施内容 鳥羽市の海女文化を調査し、現在海女さんが減少している原因を地域、環境、海洋生物など様々な観点からリサーチしました。 調査結果 事前の調査でわかっていた鳥羽市の大きな魅力である海女文化が今では昭和に比べ海女さんの人数が8分の1まで減少しているなど、今後10年、20年後に文化として残っているのか危ぶまれるという課題を踏まえ行った。調査を進めるうえで人口減少の原因として、アワビなどの海産物の減少や20代30代の海女が少なく後継者がいないという課題が明確になりました。 課題解決の提言 海女文化の素晴らしさをリサーチし、その魅力を捉えた芸術作品を創作していき、海の博物館などで展示発表する。プロジェクト・テーマ:海女文化を伝えるデザイン。作品を通して海女文化の素晴らしさを伝えることで若者たちが海女になりたいと思うように発信する。 このように芸術も海女文化の振興につなげる。 |
| 調査研究名:鳥羽市・答志島SDGsフィールドワーク2024
実施内容 今回の調査研究では、鳥羽市・答志島SDGsフィールドワーク2024として、当研究室が取り組んでいる国連SDGs(持続可能な開発目標)と地方創生の観点から、鳥羽市とくに離島における地域課題と解決そして関係人口の創出にむけて、学生主体のアクティブラーニングによるフィード調査を行いました。 現地調査に際し参加学生15名は、事前調査や鳥羽市現地とオンラインでつないでの事前セミナー(2回)を行い、濱口正久鳥羽市議会副議長や市職員のご助言等をいただきつつ、地域の持続可能な開発に関する課題の洗い出しやサステナブルな地域資源の絞り込みを行いました。これにもとづき、1.雇用と観光、2.地域づくりと観光、3.教育、4.地域文化の4つのテーマ別グループにて現地調査を行いました。各グループはテーマに即して行政、企業、NPO/NGO、住民や学校、キーパーソンを訪問等、聞き取り調査等をつうじて課題の分析、地域資源の発見と解決策を検討するとともに、関係人口の創出につとめることが出来ました。 また、アクションリサーチとして、職場体験型学習(旅館)や、環境保護ボランティア活動(海岸・漁港・地域清掃)等にも取り組み、ささやかながら地域社会に貢献しました。こうした現場での調査研究は学生の重要な学びの機会として高い効果が得られ、また地元の皆様との交流をつうじて関係人口の創出にも寄与する出来ました。 調査結果 具体的な調査研究の成果としては、次の通りとなります。調査研究発表として、「鳥羽市・答志島SDGsフィールドワーク報告会2024」を、2025年1月30日13:30~15:30にて開催しました。これを通じて、本学の学生や教員に、SDGsの視点からみた鳥羽市の地域課題やサステナビリティにむけた地域資源について広く共有することができました。現地調査でご協力いただいた鳥羽市の濱口副議長や市役所職員にもオンラインでご参加いただき、研究の成果をフィードバックすることが出来、またコメント・講評等を頂戴いたしました。なお、報告会で発表したスライド(108枚)は今後の鳥羽市の施策のご参考に、すでに濱口副議長をつうじて共有させていただいております。 また、本調査研究活動の総括として、「鳥羽市・答志島SDGsフィールドワーク調査報告書2024」を刊行いたしました(A4版、本編71頁・資料編インタビュー要録9頁、PDFファイル)。本報告書は、合宿をつうじた現地調査や報告会での議論等をふまえた次の内容となっております。第1部では、SDGsから分析する鳥羽市・答志島の地域課題とサステナビリティについて、4つのテーマにそくした学術的な分析と課題解決に向けた提言等を行っています。第2部では、各学生が現場で得られた貴重な体験や知見について、フィールドワークの振り返りを行っています。そして、資料編として、現地での訪問調査によるインタビューの要録を一次資料としてまとめています。本報告書では指導教員のもと、学生自らが執筆および編集を行い、現地調査をつうじた課題分析や課題解決の提言等をまとめることができました。 課題解決の提言 鳥羽市の文化等の豊かな地域資源と関係人口を活かした施策。 |
| 調査研究名:鳥羽なかまち地域課題研究合宿
実施内容 フィールドワークおよび地域の方へのヒアリング 調査結果 なかまち地区は商店街への観光客流入が少ないことに加えて、人口減少に伴い空き家が増加し、津波や地震への備えも必要とされているという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 ・防災と交流を兼ねた街道の整備 ・駅からなかまちへ足をのばしたくなるような仕掛けづくり ・点(見どころ)ではなく線(道)を中心としたまちづくり |
| 調査研究名:鳥羽駅前再開発にあたる事前調査
実施内容 1. 鳥羽駅前再開発に関するヒアリング 鳥羽駅前再開発の現状を把握するため、鳥羽市が設置した策定委員会に関わる関係者の方々にヒアリングを行いました。そこで共通して語られたのは、「鳥羽市民がより主体的にまちづくりを考える場が必要である」という点でした。
2. 現地視察会の開催 ヒアリングを通じて見えてきたもう一つの共通認識は、「より多様なアイデアを取り入れながら、まちづくりを進めていきたい」という思いでした。そこで、鳥羽市内はもとより全国から若者を招き、鳥羽駅周辺の活用アイデアを構想するための現地視察会を開催しました。 調査結果 調査研究により、現在進⾏中の⿃⽻駅前再開発に関して⿃⽻駅周辺で観光業などを営む⽅々が主体的に考える機会が多くなく、⾃分たちごととして捉えられていないという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 1. 地域住民や事業者を巻き込んだ対話の場の創出 鳥羽市民が鳥羽駅前再開発を主体的に捉えてもらうためには、住民や観光事業者が自由に意見を出し合い、ビジョンを共有できる対話の場が不可欠です。ワークショップや意見交換会を開催し、行政と市民が協働してまちづくりを進める体制を整える必要があります。
2. 地域内外の多様な視点の導入 市外の若者や専門家を巻き込むことで、地域の固定観念にとらわれない新たな発想を取り入れられます。そのためには、幅広いアイデアを集めるコンペ企画を実施して、鳥羽のまちづくりに関心のある人材を受け入れる仕組みが求められます。
3. 情報共有と進捗の「見える化」 再開発の方針や進捗状況が関係者に十分に共有されていないことも、市民の当事者意識の欠如に繋がっています。定期的な情報発信や、ビジュアルを用いた説明資料の作成などにより、誰もが現状を理解しやすくする工夫が必要です。別のアプローチとして2.で述べたコンペ企画で出てきた提案を鳥羽市民が集まる場所で展示をすることを提案いたします。
これらの取組を通じて、鳥羽駅前再開発が地域全体の意志によって進められるプロジェクトとなることが期待されます。 |
令和5年度
| 団体名 | 調査研究名 | |
| 1 | 女子美術大学 | 鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト |
| 2 |
東京海洋大学 水産経済・経営学研究室 |
カキ養殖漁場の利用方法と漁業者の認識に関する調査研究 |
| 3 |
東京大学 岡部明子研究室 |
モノが語る離島の漁村空間ー模型対話手法を用いてー |
| 4 |
専門学校東京ビジュアルアーツ 水中映像ゼミ |
海女さんの魅力と漁村文化の撮影 |
| 5 |
日本大学 理工学部海洋建築工学科海洋建築・建築デザイン研究室 |
本土近接型離島における観光資源・来訪環境・観光満足度の関係からみた観光のあり方 |
調査研究詳細
| 調査研究名:鳥羽ストーリーズ・アートプロジェクト
実施内容 鳥羽市の海女文化を調査し、現在海女さんが減少している原因を地域、環境、海洋生物など様々な観点からリサーチしました。 調査結果 事前の調査でわかっていた鳥羽市の大きな魅力である海女文化が今では昭和に比べ海女さんの人数が8分の1まで減少しているなど、今後10年、20年後に文化として残っているのか危ぶまれるという課題を踏まえ行った。調査を進めるうえで人数減少の原因として、アワビなどの海産物の減少や20代30代の海女が少なく後継者がいないという課題が明確になりました。 課題解決の提言 海女文化の素晴らしさをリサーチし、その魅力を捉えた芸術作品を創作していき、海の博物館などで展示発表する。作品を通して海女文化の素晴らしさを伝えることで新たな発信源を確立する。 このように芸術も海女文化の振興につなげる。 |
| 調査研究名:カキ養殖漁場の利用方法と漁業者の認識に関する調査研究
実施内容 鳥羽市浦村にて、カキ漁業者に対するヒアリング調査、アンケート調査を実施しました。その中で、漁場の区域ごとの利用方法と漁業者の漁場認識、すなわち、各漁場が、稚貝育成、出荷調整、等においてどのように利用されているか、また、漁場の環境特性(流速、クロロフィル濃度、等)についてどのように認識しているかについて明らかにしました。 調査結果 調査研究により、漁業者の漁場認識は科学的なデータと概ね整合的であるが、一部にデータよりも評価が低く今後の活用の可能性のある漁場が存在すること、また、環境変化に対しては認識の調整にややバラつきのある可能性があるという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 漁場環境やカキの成育に関する継続的な調査と、漁業者へのフィードバックが必要であると考えられます。 |
| 調査研究名:モノが語る離島の漁村空間ー模型対話手法を用いてー
実施内容 本調査研究は漁村集落の路地を構成するモノに着目し、空間をその背後にあるモノと人の連関から描き出すことを目的とした。具体的には答志島和具集落を対象としたモノを介した人のつながりを集落の模型を用いて分析した。 その調査と同時に島の交流拠点である“ねやこや”でのモノのやり取りについても整理した。そして、モノと人の連関が弱まることでコミュニティの営みに支障が生じることを踏まえて、人との関係を誘発すべくモノを動かし、手を加えることで集落内に拠点を紡ぎ出す方策を実践的に提示する。 今後全国的に過疎化が進む中で、よそ者の介入や高齢者の外出機会の減少などによるコミュニティの変化が生じている。いかにして地域のコミュニティを維持できるのかを模索していく。
調査とは直接的な関係はないが、“ねやこや”に全国各地の大学生を呼び込み、イベントも定期的に開催してきた。また、お盆や敬老会などの集落の祭りにも積極的に参加し、地域と密接に関わりながら課題と魅力を探求した。 調査結果 調査研究により、離島の漁村集落におけるモノを介した人の繋がりを見える形にし、その繋がりの連鎖を引き込むように作られたのが“ねやこや”という島の拠点であることが明らかになった。その拠点形成の過程の中で明らかになった鳥羽市と離島の課題について以下にまとめる。
1.災害や非常時の対応の仕方について 離島では人のつながり、コミュニティが強固なものであるため、非常時における対応に慣れている。例えば、災害時の避難経路は皆当たり前のように把握している。また、漁船を利用した救急船の手配の仕方も地元の中で共有されている。本来は救急船に特化した船を常時島に置いておくべきかと思うが、そこを答志島ではコミュニティによって現状カバーされている。一方で、よそからよってきた移住者にとっては、地元で当たり前に共有されていることに、ついていくことができていない。ここ数年だけでも島には多くの移住者が住んできたが、きっと非常時の対応の仕方を把握している人は少ないだろう。日々利用する定期船でも非常時の対処方法ははっきりと船内に記載されていない。このような当たり前な共有事項を再確認する必要があるのではないだろうか。
2.人のつながりが固定化されている 上記でも述べた通り離島ではコミュニティが強固である分、各世代ごとに集まることが多い。世代ごとの仲間意識は必要であるが、今後高齢者が増えていく中で、子どもたちや若い世代との関わりしろを生み出す必要がある。世代を跨いで助け合う場面が多くなると考える。
3.日本の枠組みの中での離島 日本は島国であり多くの離島が存在し、政府も離島振興法のもと地域づくりを進めている。もちろん日本の中で離島の立ち位置を確立していくことは重要であるが、もう世界の中での一つの離島という広い枠組みで捉えることができるのではないだろうか。鳥羽の離島それぞれに特別な暮らしがあり、日本の枠組みにとらわれずに広い視野を持って離島を発信していくことが課題となっていくのではないかと考えた。
1.~3.で述べたような状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 1.災害・非常時の当たり前をきちんと共有化する 例1)避難訓練の際に避難ルートを地図に書いてもらうワークショップなどを開く。 例2)定期船に非常時の対処方法を離島の小学生中学生がポスターとして掲示する。 例3)緊急搬送の際の段取りを見える形として残す。模型でワークショップを行う。 このように地域の当たり前を見える形にする必要がある。 2.“ねやこや”のようなモノを介した拠点づくりを進める モノを介することで世代や属性にとらわれずに適切な距離を保って人間関係を作ることができる。“ねやこや”のようなモノがやってくる拠点を各集落で設けることが必要である。鳥羽市内の他の漁村集落でも同様な取り組みを広げていくことを検討している。 3.海外に発信する媒体 まずは離島の情報発信を行う離島経済新聞にて、答志島の暮らしを外国語で特集するようなコーナーを寄稿することを検討している。そして、“ねやこや”には多くの大学生が訪れているため、留学生も積極的に受け入れる体制を整え、世界における一つの離島としての立ち位置を探る。 |
| 調査研究名:海女さんの魅力と漁村文化の撮影
実施内容 事前調査でも分かっていたが、現地にて海女さんの話を直接聞き鳥羽の歴史ある文化の海女文化、漁村文化が後継者不足に直面していることがより分かった。 後継者不足以外にも漁獲量の減少により、十分な収益が望みにくいという課題があることが分かった。 また、そういった後継者不足である現状や海女文化、漁村文化の魅力を県内外に向けて効果的に発信できておらず、知られていないという状況が判明しました。 調査結果 調査研究により、漁業者の漁場認識は科学的なデータと概ね整合的であるが、一部にデータよりも評価が低く今後の活用の可能性のある漁場が存在すること、また、環境変化に対しては認識の調整にややバラつきのある可能性があるという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 写真映像を使用したリアルな海女さんの活動を県内外に発信することで海女さんの現状を知ってもらい、海女文化に関わる人を増加させ、海女文化の振興につなげていく。 |
| 調査研究名:本土近接型離島における観光資源・来訪環境・観光満足度の関係からみた観光のあり方
実施内容 本土近接型離島を訪れる観光者へアンケート調査を実施し,観光者の満足度の醸成要因や観光ロイヤルティの形成要因を明らかにすることで,離島の持続可能な観光振興への知見を得る。 調査結果 離島において観光による地域振興が推進される今日,持続可能な離島観光施策を展開するためには観光者の離島への観光ロイヤルティを獲得すること(離島へのファンなるような観光経験)が重要となる。 離島への来訪はその立地により様々であるが,特に答志島などは本土の観光者は日帰りで離島を観光することが可能(以降,本土近接型離島)であり,このような離島における,観光者の観光経験は連絡船の運航状況に左右されてしまうことが考えられる。ここで,既往研究をみると離島における観光ロイヤルティの獲得に関する研究の蓄積は不十分であり,離島への来訪環境を踏まえた研究はなされていない。そのため,本土近接型離島における持続可能な観光施策の展開に向けて,観光者の観光ロイヤルティの形成要因を把握することは急務だと考える。 課題解決の提言 本研究では,本土近接型離島における観光ロイヤルティの形成モデルの実証を行い,観光ロイヤルティの獲得に寄与し得る離島観光施策を検討した。その結果,以下の事項が明らかとなった。1.本土近接型離島は136島あり,瀬戸内海周辺や九州西部に多く分布している。2.本土近接型離島を有する自治体は,島内の観光資源として自然資源や歴史・文化資源,レクリエーション資源を多く認識しているが,来訪手段が限定的であることや島内の施設整備が十分でないことから,観光者の滞在は一時的になっていることを課題として挙げている。 次に,答志島を訪れた観光者を対象に観光ロイヤルティの形成要因を把握するため,観光経験に関するアンケート調査を実施したところ,以下の事項が明らかとなった。1.観光者の島内の行動は和具港や答志港を中心とした周遊がみられ,初来訪や日帰りの観光者ほど周遊行動は広範囲かつ多岐にわたる。2.観光者の総合満足度の評価要因は来訪パターン(来訪回数及び宿泊の有無によるパターン分類)により異なるが,都市型観光資源での観光経験が総合満足度を高める上で重要な要素となる。3.観光者の観光ロイヤルティの形成要因は,来訪パターンに応じて期待度と満足度による影響度合いが異なり,初来訪の観光者は来訪前の答志島に対する期待度,2回目以降の観光者に対しては答志島の観光経験から評価される答志島としての満足度が観光ロイヤルティの形成に大きく影響する。そのため,本土近接型離島において観光者の観光ロイヤルティを獲得するためには,これら観光者の動向を考慮した離島観光施策の展開が重要となることが示された。 |
令和4年度
| 団体名 | 調査研究名 | |
| 1 |
名古屋大学大学院 環境学研究科加藤博和研究室 |
鳥羽駅周辺における来訪者向け案内表示の現状課題と改善策 |
| 2 |
横浜国立大学 島プロジェクトin鳥羽 |
第一回答志島課題研究 |
| 3 |
東京海洋大学 水産経済・経営学研究室 |
カキ養殖漁場の環境特性に関する調査研究 |
| 4 |
三重大学 生物資源学研究科 |
無形観光資源に対する観光客評価の相異に関する分析 |
| 5 |
國學院大學 観光まちづくり学部地域マネジメント研究センター |
「鳥羽うみ文化ライブラリー」の具体化に向けた基礎調査研究 |
| 6 |
芝浦工業大学 空き家改修プロジェクト未利用浜プロジェクトチーム |
未使用浜の再利用施工活動 |
| 7 |
芝浦工業大学 空き家改修プロジェクト鳥羽なかまちチーム |
お祭り企画&町おこしのための鳥羽未来会議開催 |
| 調査研究名:鳥羽駅周辺における来訪者向け案内表示の現状課題と改善策
実施内容 近鉄鳥羽駅~鳥羽マリンターミナルのフィールドワーク、地域公共交通会議での結果報告 調査結果 調査研究により、鳥羽駅から鳥羽マリンターミナル間の案内表示や経路が来訪者にとって分かりづらいという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 担当部局・所有者に対する改善案の周知、担当部局・所有者による改善 |
| 調査研究名:第一回答志島課題研究
実施内容 地元住民ヒアリング、答志島の産業体験、地域内探索 調査結果 調査研究により、観光の衰退傾向、漁業関連人口の高齢化という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 魅力を発信、稼げる漁業の実現(これから通年で研究) |
| 調査研究名:カキ養殖漁場の環境特性に関する調査研究
実施内容 鳥羽市浦村地区内の各漁場区域において採水をおこない、その水のクロロフィルa濃度、濁度、塩分濃度、pHを計測し、カキ養殖漁場の環境特性を整理した。 調査結果 調査研究により、浦村のカキ養殖漁場の環境特性が、場所により異なることが分かった。一方で、カキの斃死の問題等にアプローチしていくためには、水質と身入りの関係の整理、環境の変化に対する対応、適応の方法についても検討が必要であるという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 他の漁場(浦村以外)との連携(漁期途中での漁場の移動)の可能性についての検討、など |
| 調査研究名:無形観光資源に対する観光客評価の相異に関する分析
実施内容 漁業と観光の振興に向けた観光客の観光資源に対する認識に関する調査を行いました。 調査結果 アンケート調査から、観光客にとっての鳥羽来訪の楽しみの中で漁業と関係するものは、おいしい海産物(76.3%)、自然景観を見物すること(48.5%)、自然の豊かさを体験すること(30.8%)であった。これらの魅力は漁業によって守られているわけだが、その持続性に関わる「資源管理」や「伝統漁法」を無形観光資源として活用する場合について、認知度はどちらも半数程度となっており、関心度も半数には満たない。知っている来訪者のほとんどは、この二つが持続可能な漁業の実現に関係があると認識している。そして、全来訪者のうち、持続可能な漁業は自分に関係があると認識しているのは、6割程度であった。しかし、実際の行動を見てみると、普段、海産物の購入に際し、エコラベルやオーガニックの商品表示がある商品を優先的に選んでいる観光客は2割であった。答志島の現地視察・調査では、漁村の暮らしや市場の見学を行い、漁村文化と漁業の資源保護や鮮度保持の管理体制の密接なつながりが観光の魅力となっていることがわかった。近い将来、地元海産物の品目によっては高値や提供の停止などが予想される中、消費者の理解が必要になってくる場面で、消費者が理解を行動に移してくれなければ、鳥羽の漁業は衰退し、漁村の魅力の維持は困難となる。鳥羽市の観光にとっては重大な社会的不利が生まれる可能性があるという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 鳥羽市では海産物の豊富さが観光客をひきつける最大の観光資源であるが、それを支える持続可能な鳥羽の漁業を実現するために、消費者の漁業への興味を向上させ、サスティナブルツーリズムの一環として、観光の魅力を大切に扱うことを観光客の啓発として行っていくことが必要である。特に、鳥羽ではエコツーリズムが進んでいるが、まだまだこうした視点が大きくはない。エコツーリズムの事業者は鳥羽ならではのSDGs課題への取り組みとして、漁業理解のための橋渡しとなることが望まれる。漁業理解の取り組みは、観光客の集客にはならないと思われるが、ファンとなり、満足度やリピーター獲得に効果が期待できる。 |
| 調査研究名:「鳥羽うみ文化ライブラリー」の具体化に向けた基礎調査研究
実施内容 (1)事前調査(予備調査/文献調査) 1.「鳥羽うみ文化ライブラリー」具体化の背景条件の整理 鳥羽市を取り巻く観光の現状・課題把握 2.「鳥羽うみ文化」に関わる地域資料等の情報収集 鳥羽市立図書館資料(郷土資(史)料等)の現状 3.参考事例調査 図書館(図書)を活用した観光・まちづくりへの取組事例の収集
(2)現地調査(フィールド調査/ヒアリング調査) 鳥羽市内の観光施設や観光客の利用状況、市域の現状等を把握するとともに、「鳥羽うみ文化ライブラリー」の候補地や取り組み方を検討するため、2回に分けて市内のフィールド調査及び関係者へのヒアリングを実施した。 1.第1回調査:9/7~9/9 【フィールド調査】 鳥羽駅周辺(マリンターミナル、鳥羽マルシェ)、ミキモト真珠島、鳥羽水族館、伊勢湾フェリーターミナル、パールロード(鳥羽市立海の博物館、鳥羽展望台)、相差地区、中之郷駅、なかまち等 【ヒアリング調査】 鳥羽市立図書館(市教育委員会) 鳥羽市観光課 なかまち会会長・佐藤氏 2.第2回調査:10/20~10/22 【フィールド調査】 中之郷駅、旧鳥羽小学校、三重バリアフリーツアーセンター、石鏡地区、国崎地区、答志島(和具地区・答志地区) 【ヒアリング調査】 鳥羽歴史文化ガイドセンター(清水氏)、鳥羽ビジターセンター(滋野氏)、鳥羽市立海の博物館(石原氏)、三重大学海女研究センター(吉村氏)、鳥羽市観光協会(世古氏)
(3)「鳥羽うみ文化ライブラリー」具体化の検討及び提案の取りまとめ 調査研究成果は「令和4年度鳥羽市地域課題解決調査研究事業(「鳥羽うみ文化ライブラリー」の具体化に向けた基礎調査研究)」報告書として、提案を取りまとめた。 調査結果 (1)図書館と観光の連携に向けたこれまでの現状と取組課題 これまで図書館と観光の連携した取組実績はほとんどないものの、郷土資料が充実しており、それら資料を活用した「鳥羽うみ文化」の市民・観光客への伝え方や潜在的な観光魅力の掘り起こし・活用が期待される。郷土資料の中には重複資料も多数あり有効な活用が望まれる。 一方で、市立図書館の運営体制は十分とは言えないことから、「鳥羽うみ文化ライブラリー」を含め観光との連携推進にあたっては、要員体制にも留意が必要である。
(2)フィールド調査、ヒアリング調査をふまえた課題・留意点 1.鳥羽市の観光及び市全体の課題 観光利用の面では、玄関口である鳥羽駅~伊勢湾フェリーターミナルまでの海側のエリアに主要交通施設や観光施設が集積しており、観光客の利用もこのエリアに集中している。市域全体で見れば、相差を除き浦村、石鏡、国崎、離島などの観光利用の促進が課題である。 とりわけ旧市街地においては、歴史・文化資源が豊富にありながら十分活用されているとは言えず、観光客の姿もほとんど見かけない。それ以上に空家・空店舗、遊休施設の増加による市街地の空洞化が顕著であり、まちなかの活性化に観光を活かす視点が重要である。 2.「鳥羽うみ文化ライブラリー」候補地及び関係者の意識 鳥羽歴史文化ガイドセンター、鳥羽ビジターセンターなど、既に図書・資料コーナーを設置しているところがあり、「鳥羽うみライブラリー」としての素地がある。その他にも、交通施設や遊休施設などを活用したライブラリーの設置が考えられる候補地は多数あることがわかった。 ヒアリングを行った関係者の「鳥羽うみ文化ライブラリー」の展開への協力意向は大変高い。関係者からは、関係者が一緒に議論できる場や持続的な運営の仕組みの必要性などへの指摘や意見もあり、これらをふまえた具体化の検討が求められる。 課題解決の提言 「鳥羽うみ文化ライブラリー」の具体化にあたっては、鳥羽市の観光課題だけでなく、まちづくり(まちの活性化)の視点を加味した効果的な取組の必要性が明確になった。このことをふまえ、ライブラリーを活かした「鳥羽うみ文化」発信・交流拠点の創出を目標とした施策を推進する。 具体的には、「鳥羽うみ文化」をテーマとして、市域の各所で鳥羽らしさやその魅力、奥深さをより感じてもらい、市民と観光客の交流の促進や新たな観光の楽しみ方を提供するとともに、市民のまちへの愛着・誇りの醸成や新たな拠りどころともなる場(拠点)の創出を図るものである。 ここでは、様々なテーマをもった「鳥羽うみ文化ライブラリー」を、「鳥羽うみ文化」発信・交流拠点をまちなかに創り出すための仕掛け(装置)として位置付け、休憩所やまちの案内所、ギャラリー、カフェ、商店、集会所など、ライブラリーを設置する地区や運営主体の特性に応じた機能・施設を組み合わせて拠点の創出を図る。 こうした「鳥羽うみ文化」発信・交流拠点を市内の各地に増やしていくことで、 1.鳥羽うみ文化関連史料の充実・アーカイブ化の推進 2.“鳥羽らしさ”の発信力の向上 3.「鳥羽うみ文化」への市民理解の誘導、さらなる醸成 4.鳥羽の観光魅力の掘り起こし・深掘り 5.回遊性の向上、滞在化の促進+まちなかの活性化 6.観光客と市民との接点・交流機会の創出 7.観光まちづくりへの行政・民間・市民の連携意識の醸成 8.相乗効果の高いアクションプログラムの推進 といった相乗効果に結び付ける。 具体化にあたっては、フィールド調査・ヒアリング調査等の結果をふまえ、関係者での取組の方向性の共有化や有力な候補地におけるモデル事例づくりなど次のステップへと進めていくことが期待される。 |
| 調査研究名:未使用浜の再利用施工活動
実施内容 海洋プラスチックごみを収集、加工し唯一無二のアート作品として生まれ変わらせることで海洋プラスチックを新たな資源として人々の生活に寄り添った製品を開発している株式会社REMAREと協力し、海の駅 黒潮パールロード店の隣に位置する空き家を取り壊しシャワールームの設計から施工までのすべてを訪問期間中の2週間の間に完了させ、地域問題となっている海洋プラスチックの新たな可能性を示すことで鳥羽市の住民の方々だけでなく外部の方々にも訪れてもらい興味を持ってもらうという計画。 調査結果 調査研究により、鳥羽市の浜に打ち上げられた海洋プラスチックが浜の景観を乱し環境にも影響を与えているという問題、管理が行き届かず空き家となってしまっている物件が数多く存在しているという問題、鳥羽市全体として少子高齢化が進み人口が減少しているという問題、以上3点の地域課題が存在しているという状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 課題解決の提言 長年手つかずの状態で放置されていた空き家をただ改修するのではなく海洋プラスチック利用し空き家を改修し新しい利用目的を与えることで海洋プラスチックの新たな可能性を提案しつつこの企画自体の面白さや出来上がった建物を拠点として今後展開されていく事業に興味を持ち、足を運んでくれる人が増えれば上記で述べた3つの地域問題、鳥羽市の浜に打ち上げられた海洋プラスチックが浜の景観を乱し環境にも影響を与えているという問題、管理が行き届かず空き家となってしまっている物件が数多く存在しているという問題、鳥羽市全体として少子高齢化が進み人口が減少しているという問題の解決につながるのではないかと考えます。 |
| 調査研究名:お祭り企画&町おこしのための鳥羽未来会議開催
実施内容 以前改修したアワヘイの蔵で二日間にわたってワークショップを開催した。お祭りをテーマに、一日目は提灯や蔵の装飾を子供たちとつくり、二日目は蔵でヨーヨー釣りや輪投げ、射的などのお祭りワークショップを行った。多くの子供たちがワークショップに参加し楽しんでくれたことに加えて、移住体験に来ていた子もワークショップに参加することでナカマチに交換を抱いてくれたことは非常にうれしい成果であった。鳥羽市以外から足を運んでくれた方々も多く、アワヘイの蔵の存在を広めることができたイベントができた。 また、鳥羽市やなかまちに住む人を交えて行った鳥羽未来会議では、現在のなかまちの現状や空き家の状況、今後の課題や取り組んでいくべきことなどを話した。まちの模型を使って話すことで、飲食店の多さや空き家が多い場所などまちの状況の可視化ができたと感じる。住人の皆様も日ごろ住みながら感じていることや知っている情報をたくさん話してくださり、なかまちの良い点や課題、改修するべき場所を見つけることができたことが最大の成果だったと実感している。 調査結果 以前改修したアワヘイの蔵で二日間にわたってワークショップを開催しましたが、道に迷っていた子供たちが多く、アワヘイの蔵の存在があまり認知されていないことが問題点である。また現在スタッフがいないことや、蔵を貸すだけになっている現状を改善しなければならない。 鳥羽未来会議であがった課題としては、ひとつは観光客の流れがなかまちまで入らず、線路を超えた交流がないことが挙げられる。もうひとつはなかまちに多く飲食店があるにもかかわらず、常に空いているお店がほとんどなく観光客が訪問しても楽しめない状況になっていることである。また企業や店の誘致がしにくい状態でもある。飲食店は、平日に来る客が少なく、その原因としては鳥羽に住んでいる人も、若い人は働きに出ている人が多く、高齢者も子守などで日中にゆっくりと友人や近所の人と話す時間を持っている人が少ないことも挙げられた。加えて観光客と地元の人が訪れる場所や飲食店が異なるため、なかまちに観光に来た人と地元の人の交流が生まれにくいという点も課題である。 課題解決の提言 一つ目は現在レンタルスペースとして貸し出しているアワヘイの蔵の役割を明確にし、より多くの人に知って使ってもらえるような場所づくりを再度行うことが必要であると考える。また、なかまちで開催しているイベントをアワヘイの蔵でもおこなっていただくなど、地域に今までよりも活用してもらうことが必要である。 二つ目は、線路や駅、線路に沿った道を活用することで、線路で分断されてしまっている現状を変えていくことが必要である。今後改修する物件についても、空き家や多くの飲食店、駅など観光客を引き付けるまちの魅力を活かすことができる場所をまちの人と話し合いながらつくることが必要である。 |
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1157
ファックス:0599-25-1159
メールフォームによるお問い合わせ






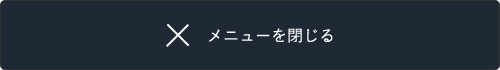




更新日:2026年02月06日